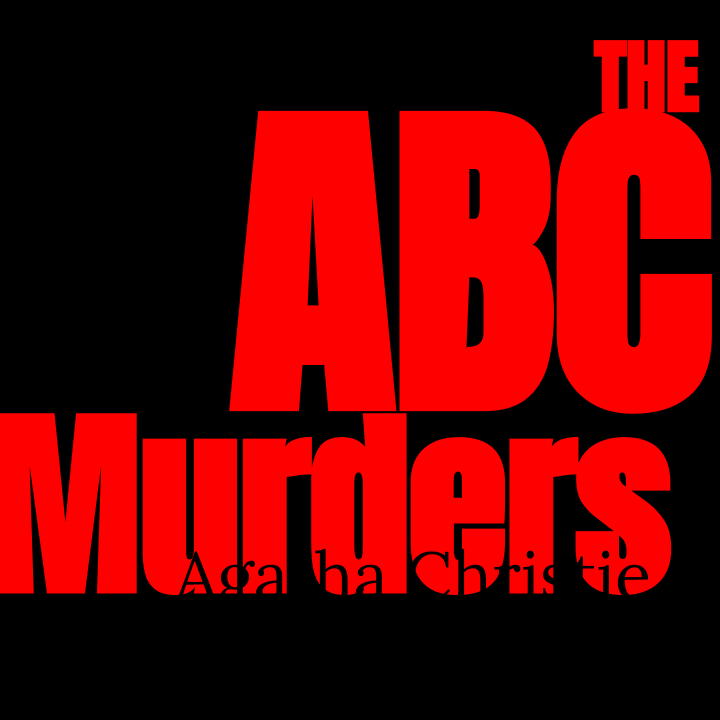これは小説だ。フィクションだ。「いかにも」、という言葉によって現実世界から乖離した、「いかにも」なフィクションだった。ただしこの「いかにも」という語は完全に現実から離れた人物を生み出すのではない。読者にとって想像し易い人物を創造する。事件解決というアクションがスポーツとなり、ドラマチックな縁結びの神となり、娯楽となる所以である。
気になった点の一つは、推理が心理的な考察に大きく寄っている点だ。心理学者まで登場するところを見ると、彼女が意図的にそれを使っているものと推察できる。上の「いかにも」という語が人物の描写でよく使われているのも、心理学的な推理を容易にするためかもしれない。この辺りはとても時代を感じた。
私の今までのサスペンス系の小説の読書歴は、おおよそポー、ジム・トンプソン、ポール・オースターによって構成されている。彼女の作品はそのいずれとも違うものだった。ポーは、それが主題ではないものの、合理的なものの考え方にある程度重点をおくため数学の証明のような趣がある。トンプソンはこれはこれで灰汁の強い作家で、アメリカを凝縮したような物凄い小説を書く。オースターはそのどれとも全く方向が違い、探偵小説の型を使って小説という概念を崩してゆくような小説を書く。ではクリスティーはどうかと、上に書いたように娯楽的な方向に行ったのではないかと一作読んだ時点で感じた。その腕前はなかなかのもので、物語の運び方がとても巧かったと思う。AからCの殺人が起こるまでは、殺人犯について全く何も分からない。犯人に精神的におかしい部分があることは分かるものの、それさえ何かの型にきれいに収まるものでもなく、無論人相についての情報なぞ皆無だ。その状況で犯行のみが進んでゆき、歯止めをかけることができない。この状況がDの事件の発生直前の探偵ポワロの閃きを皮切りにみるみる崩されてゆき、70ページほどで劇的に解決を進展させ、ひと呼吸おいて、もうひと山あるのを匂わせて読者の好奇心を誘い、その後の20ページで一気呵成に読者の認識をひっくり返し、最後に英国紳士風を吹かせてしめるという、鮮やかな運びであった。解決が停滞しているときは犯行を連発させ、そちらが繰り返しと感じられる一歩手前で謎解きを進展させることで400ページにわたって物語に緊張を途切らせない。まったく迷惑なことに目を紙上に惹きつけて止まない。困ったものである。殺人、謎解き、足掻き、解決、という一連の物事は、わが身に起これば愉快でも何でもないが、空想の中でならばなかなか愉快だ。今回ある人に勧められて初めて読んでみたのだが、とても楽しかった。